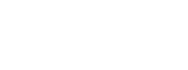座談会:サンプソンとラウブによる犯罪学の古典Crime in the makingを翻訳して(1)
Posted by Chitose Press | On 2025年04月23日 | In サイナビ!, 連載犯罪学分野の基本文献でありながら日本語に翻訳されていなかったサンプソンとラウブのCrime in the makingがこのたび翻訳出版されました。出版の経緯やいま本書を読む意義などを,4人の訳者に語っていただきました。(編集部)
――サンプソンとラウブの『犯罪へ至る道,離れる道――非行少年の人生(1)』が2025年3月に刊行されました。原著Crime in the making(2)は1993年に刊行され,犯罪学の分野で非常によく読まれ,海外ではいくつかの賞を受賞しましたが,長らく日本語には翻訳されませんでした。翻訳された4人の先生方にオンラインでお集まりいただきまして,本書刊行の経緯や意義などについてお話しいただければと思います。まず,本書の概要について,少しご説明いただけますでしょうか。
相良翔(以下,相良)
本書は,現在の犯罪学を代表する研究者であるロバート・サンプソン(Robert J. Sampson)とジョン・ラウブ(John H. Laub)によって書かれた犯罪学の古典的著作であり,ライフコース理論に基づき,犯罪の発生,持続,離脱を分析した研究です。グリュック夫妻(シェルドン・グリュックとエレノア・グリュック)によって収集された非行少年たちの縦断的データに再分析を行い,幼少期から成人期にかけて社会的絆(家族,学校,結婚,兵役など)が与える影響を明らかにしています。とくに,家庭環境や学校との関係など,初期の社会的絆が非行の開始を予測する一方で,成人期における安定した就労や良好な結婚関係といった新たな社会的絆が離脱の契機になりうることが示されてます。
 相良翔(さがら・しょう):埼玉県立大学保健医療福祉学部准教授。主要著作に,『薬物依存からの「回復」―ダルクにおけるフィールドワークを通じた社会学的研究』(ちとせプレス,2019年),「『同じ経験』と『違う経験』の狭間に臨むピア・サポート―更生保護施設および併存性障害者支援施設をフィールドとして」(『現代社会学理論研究』18: 31-43,2024年)など。
相良翔(さがら・しょう):埼玉県立大学保健医療福祉学部准教授。主要著作に,『薬物依存からの「回復」―ダルクにおけるフィールドワークを通じた社会学的研究』(ちとせプレス,2019年),「『同じ経験』と『違う経験』の狭間に臨むピア・サポート―更生保護施設および併存性障害者支援施設をフィールドとして」(『現代社会学理論研究』18: 31-43,2024年)など。
翻訳の際に気をつけた点や苦労した点
――ありがとうございます。翻訳の際に気をつけた点や苦労した点はありましたでしょうか。
相良
最初にこの本を翻訳しようという話が出たのが,たしか若手の集まり(3)で食事をしている際に吉間さんと話したときだったと記憶しています。この本を翻訳した方がいいんじゃないかという話になって,それで大江さんを誘ってスタートしました。気をつけた点,苦労した点でいうと,翻訳する際にまず索引を訳した方がいいという話になり,そこから始めたのですが最後までそこに悩まされたと思います。それぞれの単語を英語で読む分にはさほど苦労しないのですが,いざ日本語にしようとしたときにどうするかみたいなところですね。最初は3人で訳し始めて,その後に向井さんに参加していただいて,そこでまた検討してという感じだったんですけど,複数の人で翻訳したときに出てくる課題というか,難しさだったのかなって気がしますね。みなさんいかがですか。私はけっこう最後まで訳語の統一で悩みました。
吉間慎一郎(以下,吉間)
たしかに,英語で読んでいるとすんなり意味を理解できるのに日本語に翻訳すると言葉足らずでわかりにくい箇所がけっこうあって,どのように噛み砕いて翻訳するか悩みましたね。また,私が担当した章では統計用語が多く,向井さんにも助けていただきながら苦労して翻訳しました。
吉間慎一郎(きちま・しんいちろう):検事。主要著作に,『更生支援における「協働モデル」の実現に向けた試論―再犯防止をやめれば再犯は減る』(LABO,2017年),「社会変革のジレンマ―伴走者と当事者の相互変容からコミュニティの相互変容へ」(『犯罪社会学研究』44: 46-62,2019年),「包摂と排除をひっくり返す―解放区からの変革可能性」(『犯罪社会学研究』49: 25-39,2024年)など。
相良
この点どうですか。向井さん。
向井智哉(以下,向井)
そうですね。統計に関してはたしかに難しい言葉もあったかと思います。けれども,比較的王道的な言葉も多かった気もしないでもないかもしれないですかね。
 向井智哉(むかい・ともや):福山大学文化学部講師。主要著作に,『処罰と近代社会―社会理論の研究』(翻訳,現代人文社,2016年),「厳罰傾向と帰属スタイルの関連―日韓の比較から」(共著,『心理学研究』91(3): 183-192,2020年),「特定少年実名報道への支持と,責任付与・改善更生・重大性に関する各認知との関連」(共著,『心理学研究』95(2): 119-128,2024年)など。
向井智哉(むかい・ともや):福山大学文化学部講師。主要著作に,『処罰と近代社会―社会理論の研究』(翻訳,現代人文社,2016年),「厳罰傾向と帰属スタイルの関連―日韓の比較から」(共著,『心理学研究』91(3): 183-192,2020年),「特定少年実名報道への支持と,責任付与・改善更生・重大性に関する各認知との関連」(共著,『心理学研究』95(2): 119-128,2024年)など。
相良
向井さんに指摘されて,「あーなるほど」と思ったことがいくつかありました。あと統計手法の古さですよね。
向井
そうですね。たとえばこの本ではt比という統計指標が使われているのですが,現在では使われていません。また,媒介モデルを検討するために重回帰分析を繰り返しているのですが,これも現在ではほぼやられていなくて,構造方程式モデリングや媒介分析を使うことが多いと思います。このあたりの分析は参考にする必要はありませんので,お読みになるときには注意していただく必要があるかなと思います。
相良
訳者あとがきでも書きましたが,古さはやはりあって,統計を勉強していたとしても知らなくて当然だなと思ったところもありました。
相良
大江さんはいかがでしたか。
大江將貴(以下,大江)
最後に翻訳を統一するなかで,原著を読み直すと他では違う単語が使われていても,そこだけ別の単語が使用されていることがある。揃えた方がいいのかなとか思いつつ,最後は他の単語に揃えましたけど,日本語だと言葉としてはそんなに選択肢は多くないところでも英語だと何個か別の単語が使用されているところが何箇所かあって,個人的には難しさを感じました。日本語としての言いまわしに苦戦するようなところもあった記憶がありますね。
 大江將貴(おおえ・まさたか):帝京大学文学部助教。主要著作に,『学ぶことを選んだ少年たち―非行からの離脱へたどる道のり』(晃洋書房,2023年),『日本の青少年の行動と意識―国際自己申告非行調査(ISRD)の分析結果』(分担執筆,現代人文社,2024年)など。
大江將貴(おおえ・まさたか):帝京大学文学部助教。主要著作に,『学ぶことを選んだ少年たち―非行からの離脱へたどる道のり』(晃洋書房,2023年),『日本の青少年の行動と意識―国際自己申告非行調査(ISRD)の分析結果』(分担執筆,現代人文社,2024年)など。
相良
なるほど,ありがとうございます。向井さんを除く3人が翻訳書を出すのがはじめての経験になるので,そういうところやどこまで噛み砕いて訳していいものかとかは僕にもありましたし,大江さんにもあったということですよね。サンプソンとラウブについて,この本やその他の著作を読んだ限りですが,彼らの言い回しを想像しながら翻訳していたのですが,初心者だったので結局苦労しました。
向井
統計以外のところで意識したところに関して,なるべくわかりやすくするように心がけていましたね。とくに歴史に残る古典的な名著ということで,なるべく多くの人に読んでいただきたいなと思っていて,研究者以外の方であっても,実務家や単純に犯罪に興味がある人に読んでいただきたいなと思っていましたので。統計とかテクニカルな用語や変数名は統一しないとまったく意味が通じなくなってしまうので統一しましたが,それ以外のところに関しては統一するよりも,日本語として自然に読んでいただけるようにというのを意識していました。どれほどうまくいったかわからないですけれども。同じ英語が使われているからといって,絶対に一対一対応させなくちゃいけないとかは個人的には思ってなかったですね。どんな言葉でも,文脈によって日本語で違うこともあるので,そのあたりは本当に読みやすさ重視で,言い方は悪いかもしれないですけれども,雰囲気で翻訳したところはありました。
相良
たとえば,付録のインタビューに出てきた単語と,前の章で出てきた単語の訳し方はやっぱり多少変えないと変だなというのがありました。
向井
そもそも「インタビュー」という言葉自体を変えていましたよね。他のところでは面接調査とかにしていましたが,付録では「インタビュー」にしていました。
相良
そうですね。どう統一するかに関しては,文脈に応じてという形でした。
向井
そうですね。一対一対応させるのだったらAIでやってもらえば早いですし正確なので,不統一感というかわかりやすさが人間らしさみたいでいいのかなとは個人的には思っています。統一できてないところがあった場合の言い訳ではないですけれども。
相良
AIに全部やってもらったわけではないみたいな。
向井
人間の味ということで。
相良
この本を訳してる間にAI翻訳に関して,めちゃくちゃ機能が上がっていったじゃないですか。AIの精度が上がっていったら人間が訳す意義ってどこにあるんだろう,みたいなことはじつはちょっと意識はしていました。
向井
そうですね。たぶんいまの時点で研究者も含めて99%の日本人よりも英語がうまいですよね。ChatGptに,もう人間は勝てないですよね。ただ,たぶんニュアンスのわかりやすさとかはAIにはできないことだと思うので。
相良
本書を訳していて文構造がすごい難しい文章もあって,正直なところそこはAIに頼りました。正確に訳したいなと思ったので。でも,訳としては合っているけど読みにくいというか訳が固いな,ということもあって,そのままは使えないなあとは思いましたね。ここに参加されてるみなさんも実感されていると思いますけれど,AI翻訳はすごいので,今後ももし人間が翻訳するうえで,その本の背景とか著者のことをより知らないとうまく訳せないし,意味や意義が薄れていくような気がしました。翻訳のハードルが上がったなって感じますね。ただ訳せばいいだけじゃないんだってところですね。翻訳の初心者が言うのもあれですが。
――なるほど。
向井
僕も使っていたんですけれども,ライバルと思って使っていましたね。自分で訳してみてその後にChatGPTに翻訳させて,ここは僕の方がうまいなとか。ここはChatGPTがうまいなみたいな感じで使っていました。
相良
まったく一緒です。負けたのもありますよ,正直。
向井
はい,たぶん僕も負け越している気がします。
相良
吉間さんと大江さんはそのあたりどうでしたか。
吉間
僕はDeepLを使いました。DeepLの訳の方がわかりやすいと思うときは多々ありましたが,それでも日本語として自然な文にするという点は負けじと頑張りました。
大江
私は担当しているところに,専門的でも全然なくてよく知らないところがあったので,そこはもう純粋に頼って,確認して訳し直すというような感じで使いましたね。私はDeepLとChatGPTの2つを使いましたが,微妙に差はありますよね。用語が多少ぶれて出てくるので,そこはやはり人の力かなと思いました。
相良
そうですよね。本の中の中心概念である「離脱」,desistanceの訳がChatGPTとかでは出ない。だいたい「離脱」ではなくて「脱離」と出てくる。僕が使ったかぎりで,みなさんの場合はどうだったかはわからないですけど。特殊な意味なんだなと,逆に気づきました。そういう意味では,あまり頼りすぎてはいけないなと。概念のニュアンスみたいなところがAIだとまだつかみにくいということを感じました。
向井
僕のChatGPTではdesistanceを「離脱」と翻訳しますね。
相良
あ,出ますか。俺だけ「脱離」なのかな。
向井
いまさらですけど,「脱離」も悪くなかったかもしれないですね。概念であることが明確になるので悪くない気がしますね。
相良
desistanceの概念が早めに統一できてよかったですけど,向井さんが言うとおりもうちょっと考えるべきところではありましたよね。desistanceという言葉を使って本が書かれたのはいつ頃なのかは僕も把握できていないのですけど,時代的にしようがないのかなと思いつつ検討すべきところだったかなとは思いますね。離脱研究が2000年以降に増えるので,この本が1993年に出たからもうちょっと後なんでしょうね。この本あたりから,そうした離脱に関する議論がなされてきたのでしょうね。
向井
その後の犯罪研究への影響ということですね。
相良
アメリカがサンプソンとラウブで,イギリスではファリントンの研究がありますよね。
向井
ファリントンの研究だとピッツバーグ青年研究がありますね(4)。だいたい1500人ぐらいが入っているコホート研究だった気がします。
相良
大規模なことをやりだしていますよね。サンプソンたちの影響を受けてやったんだろうなと思います。この本の特徴はいわゆる量と質を合わせてやったところにあって,とくに質的調査の方が有名です。そもそも犯罪学の中でライフストーリーを研究するのはオーソドックスな手法であり,そこから離脱研究が増えていったかと思います。
(所属は出版時のもの)
文献・注
(1) ロバート・J. サンプソン,ジョン・H. ラウブ/相良翔・大江將貴・吉間慎一郎・向井智哉訳,2025『犯罪へ至る道,離れる道――非行少年の人生』ちとせプレス
(2) Robert J. Sampson and John H. Laub, 1993, Crime in the making: Pathways and turning points through life, Harvard University Press.
(3) 犯罪・非行を研究する若手研究者ネットワーク(The Early Career Criminology Research Network of Japan)
何が少年たちの人生を分けたのか? ライフコースを通じて,犯罪や逸脱行動を繰り返す人と犯罪や逸脱行動から離脱する人とを分ける要因は何か。多面的な指標が含まれる,グリュック夫妻による1000人の長期縦断調査データを再構築・再分析し,年齢に応じたインフォーマルな社会統制理論を提唱した記念碑的名著。