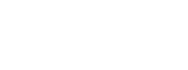感情が不安定な人は,助けを求めにくいのではないか?
『パーソナリティ研究』内容紹介
Posted by Chitose Press | On 2025年11月07日 | In サイナビ!, パーソナリティ研究困ったときに他者に助けを求めるかどうかに、本人の特性はどう関係するのでしょうか。本研究ではポジティブな感情やネガティブな感情が安定しているかどうかが、他者に対する援助の求めやすさにどのように影響しているのかが、経験サンプリング法をもとに調査されました。(編集部)
本間真凜(ほんま まりん):弘前大学大学院保健学研究科修士課程2年。→webサイト
援助要請
自力では対処できない問題に直面した際などに,他者に援助を求めることは「援助要請」と呼ばれ,これまでさまざまな研究が行われてきました。援助要請研究における重要な問題点として,深刻な問題を抱えていながらも助けを求めない人の存在が挙げられます。私の研究では,援助要請に影響を与える要因として「感情」に焦点をあて,研究を行いました。
感情の不安定性と援助要請
私たちは日々様々な感情を体験し,生活しています。感情の高低の波が激しい人や比較的安定している人など,日常の感情変化にも個人差がありますが,この「感情の不安定性」が援助要請を抑制する要因として働いているのではないかと考えました。たとえば,ある時点ではネガティブな感情を抱いていたのに,その後ポジティブ感情へ移り変わるという短期的な感情の変動が大きい場合には,一時的に症状が改善していると誤認することで,自身の症状の深刻さを過小評価しやすく,結果として援助要請の判断を妨げる要因として働くのではないかと考えました。
研究の概要
本研究では,大学生・大学院生を対象に感情の不安定性が援助要請に及ぼす影響を検討しました。感情の不安定性については,「経験サンプリング法」という手法を用いて,1週間の間,毎日2回の頻度で,現在の気分(ポジティブ感情・ネガティブ感情)について尋ねるPANAS尺度を用いて測定しました。また,援助要請に対する態度を測定する被援助志向性尺度と1週間の間に行った実際の援助要請行動の回数を尋ねました。調査で得られたポジティブ感情とネガティブ感情の変動の軌跡については,図1を参照してください。
図1
結論と今後の展望
分析の結果,ネガティブ感情の不安定性が被援助志向性に負の影響を与えることが明らかとなり,仮説が支持されました。したがって,ネガティブ感情の不安定性が高い人に対して援助要請を促進するための何らかの支援が必要であると考えられます。これに対して,ポジティブ感情の不安定性は援助要請行動に正の関連をもつことが明らかとなり,仮説とは異なる結果が得られました。ポジティブ感情の不安定性が高い,すなわちポジティブ感情が喚起されやすい性質は,行動のレパートリーを拡げ,援助資源へのアクセスを容易にすると考えられ,適応的に機能する可能性が考えられます。
本研究による知見は,感情の不安定性が援助要請に与える影響を明らかにすることで,援助を求めにくい人の特徴を理解し,メンタルヘルスサービスの質の向上やそのアクセスの改善に必要な施策を考案するうえでの指針となると考えられます。今後は,援助要請の関連要因の中でも,とくに援助要請を促進する要因について焦点をあてて,具体的な支援方策に関する検討を行いたいと考えています。
論文
本間真凜・小河妙子 (2025).「感情の不安定性が援助要請に及ぼす影響」『パーソナリティ研究』34(2), 204-215.