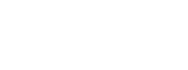クラスの雰囲気は,勉強中の助けの求め方に影響する?
『パーソナリティ研究』内容紹介
Posted by Chitose Press | On 2025年11月01日 | In サイナビ!, パーソナリティ研究勉強中に難しい問題や分からない問題に出会ったとき,どのように助けを求めるか(学業的援助要請)は学級環境(目標構造)によって違いはあるのでしょうか。学業的な目標構造と社会的な目標構造の2つの目標構造が学業的援助要請にどう影響するのか,また学業的な目標構造と社会的な目標構造がどう関係するのか,中学生を対象とした調査が行われました。(編集部)
川本心羽(かわもと みう):名古屋大学大学院教育発達科学研究科心理発達科学専攻博士前期課程2年。
「ねぇねぇ,答え教えてくれない?」は世界共通
突然ですが,中学校の頃の授業場面を思い出してみましょう。授業中,先生が前に立って例題の説明をしています。説明を終えた先生が「では,例題の下にある確認問題を解いてください」と告げます。この先生は,解答の時間が終わったら子どもを指名し,みんなの前で発表させます。問題に目を移したところ,なんとも複雑な問題でした。そこで,学生時代のあなたは,どのような行動をとっていたでしょうか。一度自分で考えてみて,それでも分からなかったら近くの人に助けを求めていましたか。「もういいや」と諦めて,隣の席の子に答えを聞いていましたか。なかには,何らかの理由で助けを求めなかった,という人もいるかもしれません。
このような,難しい問題や分からない問題に出会ったとき,どのように助けを求めるか(もしくは求めないか)に着目した研究があるのです。勉強中に助けを求める行為を,研究の世界では「学業的援助要請」と呼んでいます。この学業的援助要請は,海外でも多くの研究が行われており,下表のような分類までされているのです。当たり前のことかもしれませんが,海外であっても,勉強中に「答えを教えてほしい…」となる場面は存在しているのです(少なくとも,研究の対象となるくらいには)。
| 学業的援助要請 | 適応的援助要請 | 一度自分で考えてから援助を求める。 |
| 答えではなく,ヒントを尋ねる。 | ||
| 依存的援助要請 | 自分で考えることなく,すぐに援助を求める。 | |
| 答えを尋ねる。 | ||
| 援助要請の回避 | 援助が必要であるにもかかわらず,要請しない。 |
学級環境が援助の仕方に影響する?
先ほど,援助要請の場面を思い浮かべていただきました。そのとき,援助を求めるか否かに先立って,「みんなの前で答えを間違えたら恥ずかしい」というプレッシャーがあったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。プレッシャーを感じる学級環境だったからこそ,不正解を避けるために,あまり考えることなく「答えを教えて」と近くの席の子を頼った可能性も考えられます。この事例から,援助を求める前の段階で,その学級環境の力が働いているのでは?という問いが浮かび上がります。
したがって,この研究では,学級環境を学業・社会の両側面から捉え,学業的援助要請への影響を検討することが目的の一つでした。本研究は,学級環境を「目標構造」という視点から捉えました。目標構造は,学級の雰囲気や風土を,より動機づけ的な側面に注目して捉えたものになります(下表参照)。
| 学業的目標構造 | 熟達目標構造 | 努力することが重視される |
| 遂行目標構造 | 高い成績・テストの得点などが重視される | |
| 社会的目標構造 | 向社会的目標構造 | 思いやりや互恵性が重視される |
| 規範遵守目標構造 | ルールを守ることが重視される |
これまでの学業的援助要請に関する研究は,学業的目標構造を用いたものが主流でした。しかしながら,学業的援助要請は,相手の存在があってはじめて成立するものであるため,教師―生徒間または生徒どうしのコミュニケーションといった社会的側面にも目を向けることが重要です。とくに日本の子どもたちは,日々,学級単位で学校生活を送っています。そのため,各クラスの社会的目標構造が生徒の学業的援助要請に及ぼす影響は,無視できないものと考えられます。
研究の結果
調査は1学期と2学期に1回ずつ行い,2回とも回答した中学校1~3年生903名が分析の対象となりました。分析の結果から,1学期の向社会的目標構造の知覚が2学期の適応的援助要請を促進し,援助要請の回避を抑制する可能性が示されました。また,目標構造どうしの関係に注目すると,1学期の熟達目標構造の知覚が,2学期の社会的目標構造の知覚を高めることや,1学期の向社会的目標構造の知覚が,2学期の遂行目標構造の知覚を抑える可能性が示されました。これらの結果から,「自分のクラスでは,思いやりが大切にされている」と感じた生徒たちほど,援助が必要なときには回避せず,ヒントを教えてもらうような適応的な求め方を実行する可能性が考えられます。また,思いやりが重視されていると感じた生徒たちほど,競争的でプレッシャーのある学級だと感じにくくなることが推察されます。
おわりに
研究結果から,学業的援助要請は学級環境の社会的側面の影響を受けることが示唆されました。学習において望ましい助けの求め方が実行されるためには,思いやりのある学級環境をつくることが大切だといえます。また,思いやりや互恵性が重視される学級環境をつくるうえで,個人の努力や進歩が尊重される「熟達目標構造」の役割も重要になります。
現在,私は学級環境に着目した研究を引き続き行っております。そして,来年度からは教員として学校教育に携わる予定です。子どもたちが学びを深め,楽しく生活できる学級環境の構築について,研究および実践の立場から考え続けてまいります。
論文
川本心羽・石田靖彦・中谷素之 (2025).「学級の学業的・社会的目標構造と学業的援助要請の相互影響過程――交差遅延パネルモデルを用いた短期縦断的検討」『パーソナリティ研究』34(2), 138-147.