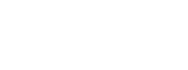座談会:サンプソンとラウブによる犯罪学の古典Crime in the makingを翻訳して(3)
Posted by Chitose Press | On 2025年05月09日 | In サイナビ!, 連載犯罪学分野の基本文献でありながら日本語に翻訳されていなかったサンプソンとラウブのCrime in the makingがこのたび翻訳出版されました。出版の経緯やいま本書を読む意義などを,4人の訳者に語っていただきました。第3回(最終回)は長期縦断研究の意義や難しさ,犯罪や非行への取り組みへの示唆について。(編集部)
長期縦断研究の意義や難しさとは?
向井
そういう変数を除外すると結果がどうなるのかというのは興味ありますね。この分析に使ったデータって公開されてるんですかね。
 向井智哉(むかい・ともや):福山大学文化学部講師。主要著作に,『処罰と近代社会―社会理論の研究』(翻訳,現代人文社,2016年),「厳罰傾向と帰属スタイルの関連―日韓の比較から」(共著,『心理学研究』91(3): 183-192,2020年),「特定少年実名報道への支持と,責任付与・改善更生・重大性に関する各認知との関連」(共著,『心理学研究』95(2): 119-128,2024年)など。
向井智哉(むかい・ともや):福山大学文化学部講師。主要著作に,『処罰と近代社会―社会理論の研究』(翻訳,現代人文社,2016年),「厳罰傾向と帰属スタイルの関連―日韓の比較から」(共著,『心理学研究』91(3): 183-192,2020年),「特定少年実名報道への支持と,責任付与・改善更生・重大性に関する各認知との関連」(共著,『心理学研究』95(2): 119-128,2024年)など。
相良
データ・アーカイブが必要だよね。
 相良翔(さがら・しょう):埼玉県立大学保健医療福祉学部准教授。主要著作に,『薬物依存からの「回復」―ダルクにおけるフィールドワークを通じた社会学的研究』(ちとせプレス,2019年),「『同じ経験』と『違う経験』の狭間に臨むピア・サポート―更生保護施設および併存性障害者支援施設をフィールドとして」(『現代社会学理論研究』18: 31-43,2024年)など。
相良翔(さがら・しょう):埼玉県立大学保健医療福祉学部准教授。主要著作に,『薬物依存からの「回復」―ダルクにおけるフィールドワークを通じた社会学的研究』(ちとせプレス,2019年),「『同じ経験』と『違う経験』の狭間に臨むピア・サポート―更生保護施設および併存性障害者支援施設をフィールドとして」(『現代社会学理論研究』18: 31-43,2024年)など。
向井
現代的な手法で分析しなおしたらどうなるのかとか関心はあります。
相良
この本だけじゃないですけど,データ・アーカイブでとっておいて,二次使用ができるようになっているとありがたいですよね。概念が時代によって変わりゆくものだとするならば,それに合わせて従属変数も変えられるので,壊すだけではなくて作ることも考えられるといいのだろうなと思います。
――犯罪関係の大きい重要な研究のデータというのは,公開されているものなのですか。
向井
あまり公開されていないですが,公開するべきという要請は非常に強く存在してますね。今回の研究は違うと思いますけれども,最近行われているような大規模な調査はだいたい税金で行われていて,税金で行われている以上,研究者だけに独占させるのではなくて社会に出してという要請がありますので,なるべく早く公開するようにという動きはあると思います。ただ研究者としては,なるべく手元に置いておきたいところもあって,公開してデータや結果が違ったら面倒なので,対立があるという感じですかね。日本での被害者調査も公開されていないですよね。
相良
たしかにしていない。
向井
あれも公開するべきですけれども,してないですよね。そういうのがいろいろとあると思います。
――他に犯罪関係の大きい長期縦断研究にはどういうものがありますか。
向井
あまりない気がします。被害者調査が世界で一番大きいと思いますが,あれは被害を受けた人なので,犯罪はどこで起きやすいのかは研究できるのでよく使われていますけれども,他にみなさんはご存じですか。
吉間
最近,日本だと法務総合研究所が2018年に行った『青少年の立ち直り(デジスタンス)に関する研究(1)』があります。
吉間慎一郎(きちま・しんいちろう):検事。主要著作に,『更生支援における「協働モデル」の実現に向けた試論―再犯防止をやめれば再犯は減る』(LABO,2017年),「社会変革のジレンマ―伴走者と当事者の相互変容からコミュニティの相互変容へ」(『犯罪社会学研究』44: 46-62,2019年),「包摂と排除をひっくり返す―解放区からの変革可能性」(『犯罪社会学研究』49: 25-39,2024年)など。
向井
ありがとうございます。読んでみます。
吉間
グリュック夫妻の研究とは異なり,継続率はかなり低くかったと思います。
向井
長期縦断調査は継続するのが難しいです。
相良
どれぐらい脱落するんですか。Wave 1,Wave 2,Wave 3とどんどん脱落していきますよね。
向井
この本では継続率がすごい高いなと思ったんですよ。
吉間
88%とかなり高い継続率でしたね。
向井
僕は基本的に1年後だったら半分になるというか,1年に限らず2回目に調査をやろうとしたら半分以下になり,繰り返すごとに半々で落ちていく感覚です。
相良
私もそれぐらいの感覚ですね。
向井
それと比べてずいぶん高い。
相良
そうですよね。それから考えたらかなり残っているんですよね。どうやって追いかけたんだろうっていうところも気になります。
向井
すごく気になりますね。回答してくれた人を追いかける大変さは論文には書かれないんですけど,めちゃくちゃ頑張るんですよね。何度も何度も電話したりメールしたり手紙を出したりして。一時期そういう研究をやったときにすごく大変だったので,この本の背後にもたぶんすごい頑張りがあったのだと思いますよ。グリュック夫妻自身ではないでしょうけれど,チームの人がすごく頑張ったはずなので,そういう人の頑張りが結果に出ていると思います。
相良
いまこれをやろうと思ってもやりきれないですよね。頑張りも難しいし,長期的に追いかけられること自体がストレスになる可能性もありますよね。
向井
そうでしょうね。
相良
吉間さんの先ほどの話じゃないですけど,対象となる人に,いつまでも犯罪や非行を行ったことを尋ねることになると思うので。本書のインタビュー場所がどこだったのかも気になって,家でやったとか職場でやったとか書いてありましたが,いまだとなかなかできないことですね。単純に追跡率を上げる地道な作業も大変だし,場所を設定するのもすごい大変だし,そういう意味では素朴にすごいなって思いましたね。そのデータが奇跡的にハーバード法科大学院の図書館に眠っていたというのもすごい。社会調査の観点で読んでみても面白いなと思ったんです。今後はやはり,犯罪や非行はなおさらですが,それ以外でも社会調査は絶対やりにくくなると思います。長期縦断調査のツールはいろいろとあるし,ウェブであの追いかけることができると思いますけど,じゃあそれで追跡率が上がるかというとそうでもないような気もしますので。
向井
たしかにそういう読まれ方もある気がしますね。実際の分析の点ではかなり古いところはあると思いますけれども,社会調査の形式的な部分に関しては現在でも参考にできるところが多々あると思います。あと分析に関しても妥当性や信頼性をしっかりと検討しているところとか,社会調査のあり方は現在でも非常に参考になるなと思いますね。
相良
今回の翻訳で再度読み直して,違う読み方になったのはそこでした。しっかり真面目に着実にやっていて,その貢献はきちんと言わないといけないと思います。これぐらいの調査をして本を書く人は,そうそういないと思うので。
向井
たしかにいろいろな読み方ができるかもしれないですね。実際に社会調査とか経験したことがない人は,調査はデータを集めているだけとかアンケートに答えてもらってるだけとか思うかもしれないですが,やってみたら意外と大変なんですよね。自分でやったことがあるかないかで,読み方も変わるかもという気がします。慣れている人から見たら,ここはたぶん苦労したんだろうなとか,1行とか2行とかで書いてあるところでも感じるところがあるかもしれません。
相良
逆に言うと,やはりデータ・アーカイブの重要性ですね。長期的な縦断調査はやりにくいだろうし,やられたとしても,限られた人がやることになると思いますけど,税金を使って実施するという話なので公共のものにすべきところですよね。
向井
長期縦断調査の意義としては,縦断調査をやると因果関係がわかりやすくなると言われていまして,単純な横断調査だとどちらが原因でどちらが結果なのかがなかなかわからないのですが,今回のようにある程度長い時間かけて何回も調査したりすると,この変数が結果で犯罪が原因だ,みたいな主張をしやすくなるという意義があります。知見として非常に強くなるという意義が,今回のデータに関してもあるのかなと思いますね。
相良
そういう意味では強いエビデンスになって,その強いエビデンスが両義的なとこもあるというのが先ほどの議論とつながってくるところかなと思います。
向井
たぶん,日本に限らず他のところでもこれからこれくらいの調査はなかなか出てこないだろうなという気がしています。というのも,いまは研究の領域で「publish or perish」という言い方があるのですが,論文をたくさん出さないと仕事が見つからないとか次の助成金もらえないとか,研究者として退場させられてしまいます。そういうふうな要請が強くあって,どの助成金も1年から長くても5年ぐらいで終わっちゃうので,長い時間をかけて調査することがもうできない状況になっています。こういう調査はもうこれから出てこないような気がしますね。
相良
違う研究グループと一緒に離脱のレビュー論文を書かせてもらったのですが(2),犯罪学の実証研究では量的調査が基本的に多くて8割ぐらいを占めるのですけど,離脱研究に限っては質的調査と量的調査が半々くらいだったんですよね。それはやはりアンケート調査をやりにくいとか,縦断調査をやりにくいというのもあるし,向井さんがおっしゃったように,早く成果を出さなきゃいけないみたいなプレッシャーの中で,それで比較的時間がかからなくてすぐできるインタビュー調査でデータを収集して分析する論文が増えているということはありますよね。実際はインタビュー調査も奥深いものなのですが。
犯罪や非行への取り組みへの示唆とは?
相良
日本の犯罪や非行への取り組みへの示唆に関しては,繰り返しになりますが,頑健な知見ではあるけれども前提を踏まえて受け取った方がよいということと,犯罪概念に関しても刑法の定義に沿って行っている部分もありますし,アメリカという文脈も重要です。たとえば兵役が離脱に効いてくるみたいな話があるからといって,日本にそれを導入してほしいとはまったく思わないので,そういう前提をもとに考えるべきところかなと思います。みなさんの方で何かありますか。
吉間
やはりこの本の内容を単純化して,犯罪からの離脱には就職と結婚をさせればよいとなってしまわないように注意しないといけないと思います。本の中でも単なる結婚と仕事があるだけでは,犯罪の減少に効いてないというのは指摘されていますけれど,仕事や結婚生活の位置づけが時代によって変わってきていますし,支援という名のもとに,研究によるエビデンスがあるとして本人が希望しないような就職や結婚を勧めることには,倫理的な観点でも問題も生じてくると思います。この本がもたらす示唆をもう一歩進めると,結局,人は社会への帰属感とか愛着が大事だという趣旨になると思うので,支援職や社会の側が,人々が帰属感や愛着をもてる社会・コミュニティをつくっていくにはどうしたらよいかを考えていくことが大事だと思います。
相良
そうですね。大江さんはいかがですか。
大江
いま話されたのはそのとおりだと思います。他に,この本はやはりライフコースが一番の鍵になっていて,ライフイベントがどういう影響をもたらすかというのが基本的な着目点だと思いますが,ライフコースが非常に多様化してきていると言われてきていると思うので,ある年代でこういうイベントが起こるというのがなかなかあてはまりにくい。日本に限らず,世界的に見てそうだと思いますけれども,この枠組み自体が問い直されていると言いますか,ライフイベントの枠組みに沿わない部分があるのかなとは思います。ライフコースの枠組みがあるからこそ,この研究は成立しているとも思いますが,ライフコースの多様性に関して,今日話をするなかでそういったことも少し感じました。
 大江將貴(おおえ・まさたか):帝京大学文学部助教。主要著作に,『学ぶことを選んだ少年たち―非行からの離脱へたどる道のり』(晃洋書房,2023年),『日本の青少年の行動と意識―国際自己申告非行調査(ISRD)の分析結果』(分担執筆,現代人文社,2024年)など。
大江將貴(おおえ・まさたか):帝京大学文学部助教。主要著作に,『学ぶことを選んだ少年たち―非行からの離脱へたどる道のり』(晃洋書房,2023年),『日本の青少年の行動と意識―国際自己申告非行調査(ISRD)の分析結果』(分担執筆,現代人文社,2024年)など。
相良
向井さんはどうしょうか。
向井
日本の犯罪や非行への取り組みという面では,この本の成果が実践においてはすでにある程度取り入れられて吸収されているところがあるようにも思います。絆や愛着が大事だよねとか,就職支援をしようとかに関しては,かなり取り組みとしてやられていると思いますので,それに対して理論的バックボーンをきちんと理解しなおすという読み方になるのかなという気がします。現在の取り組みを変えるような変数や理論モデルが出されてはいないような気はします。そんなことはないですかね。
――この本の成果を取り入れた結果がいまの取り組みということですね。
向井
いまの支援のあり方に近いのかなという気がします。だから答え合わせ的に読むみたいな感じでしょうか。逆に言うなら,この本の中で主張されているけれども,まだうまくいまの刑事司法や福祉に反映できていないところがあったとしたら,そういうところを探してたり,あてはまるか考えたりしてみると面白い読み方になるかもしれないです。
――この本の中で刑務所に入ることの悪影響みたいな話が書かれてて,この頃からそういう発想があったんだと思って,面白かったです。
相良
ああ,そうですね。そこはラディカルな意見にはなっていましたよね。
向井
ラベリング理論からの発想ですよね。きっと。
相良
ラベリング理論を実証したような分析結果になってましたよね。
向井
それはいまの政策にはあまり反映されてないかもしれないですね。社会内処遇の動きもあることはあると思いますが,どうなんでしょう。
吉間
されてないでしょうね。刑の選択や宣告する刑の重さを決める際,刑務所で服役することの悪影響は考慮されていないと思います。現在の刑事裁判では行為責任という考え方を中心として量刑が決められていますので。
向井
なるほど。その行為責任のハードルが下がっているとかはないですか。刑務所に行くべき行為責任のハードルがあって,それがその下がっているとかもないですか。
吉間
刑事裁判で実刑となるハードルが下がってきているのかはなんとも言えませんが,たとえば殺人で言い渡される刑が重くなってきているということは言われていますよね。それから,法定刑の方に着目すると,法定刑の上限や下限が引き上げられた例はたくさん挙げられますが,法定刑が下げられた例としては窃盗罪に罰金が創設されたくらいだと思います。ただ,罰金が創設されたことによって,処罰範囲が広がったとも評価できますし,実刑になりにくくなったというわけでもないと思います。
向井
下げられてるのは,たしかにほぼないですよね。
――そろそろお時間ですが,最後に何かありますでしょうか。
相良
訳者あとがきでも少し触れましたが,サンプソンとラウブの研究の続編(3)が原著で出ていて,そちらも評価されています。みなさんの余力次第ではありますが,頑張って続編も出したいなとは思っています。
向井
そうですね。頑張りましょう。
――そのためにも,この本が多くの方に関心をもって読んでもらえるといいなと思っています。本日はありがとうございました。
(所属は出版時のもの)
文献・注
(1) 法務総合研究所,2018,『青少年の立ち直り(デジスタンス)に関する研究』法務総合研究所研究報告58.
(2) Sagara, S., Suzuki, M., Hashiba, N., Yamawaki, N., Takenaka, Y., 2024, Mapping desistance research: A systematic quantitative literature review from 2011 to 2020. Journal of Offender Rehabilitation.
(3) Laub, J. H., & Sampson, R. J, 2003, Shared Beginnings, Divergent Lives: Delinquent Boys to Age 70, Cambridge: Harvard University Press.
何が少年たちの人生を分けたのか? ライフコースを通じて,犯罪や逸脱行動を繰り返す人と犯罪や逸脱行動から離脱する人とを分ける要因は何か。多面的な指標が含まれる,グリュック夫妻による1000人の長期縦断調査データを再構築・再分析し,年齢に応じたインフォーマルな社会統制理論を提唱した記念碑的名著。