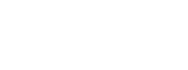座談会:サンプソンとラウブによる犯罪学の古典Crime in the makingを翻訳して(2)
Posted by Chitose Press | On 2025年04月28日 | In サイナビ!, 連載犯罪学分野の基本文献でありながら日本語に翻訳されていなかったサンプソンとラウブのCrime in the makingがこのたび翻訳出版されました。出版の経緯やいま本書を読む意義などを,4人の訳者に語っていただきました。第2回はいまこの本を読む意義はどこにあるのかについて。(編集部)
現代に,この本を読む意義はどこにあるのか?
相良
一番の疑問は,なぜいままで訳されなかったんだろう,ということで,もうちょっと早く訳されていてもよかったのかなと思います。
 相良翔(さがら・しょう):埼玉県立大学保健医療福祉学部准教授。主要著作に,『薬物依存からの「回復」―ダルクにおけるフィールドワークを通じた社会学的研究』(ちとせプレス,2019年),「『同じ経験』と『違う経験』の狭間に臨むピア・サポート―更生保護施設および併存性障害者支援施設をフィールドとして」(『現代社会学理論研究』18: 31-43,2024年)など。
相良翔(さがら・しょう):埼玉県立大学保健医療福祉学部准教授。主要著作に,『薬物依存からの「回復」―ダルクにおけるフィールドワークを通じた社会学的研究』(ちとせプレス,2019年),「『同じ経験』と『違う経験』の狭間に臨むピア・サポート―更生保護施設および併存性障害者支援施設をフィールドとして」(『現代社会学理論研究』18: 31-43,2024年)など。
向井
犯罪関連の本ってほとんど訳されてないですよね。古典的な本であっても。僕の専門の刑罰についてもそうです。あまり売れないんですかね。ブレイスウェイトのCrime, shame and reintegration(1)も訳されていないですし。
 向井智哉(むかい・ともや):福山大学文化学部講師。主要著作に,『処罰と近代社会―社会理論の研究』(翻訳,現代人文社,2016年),「厳罰傾向と帰属スタイルの関連―日韓の比較から」(共著,『心理学研究』91(3): 183-192,2020年),「特定少年実名報道への支持と,責任付与・改善更生・重大性に関する各認知との関連」(共著,『心理学研究』95(2): 119-128,2024年)など。
向井智哉(むかい・ともや):福山大学文化学部講師。主要著作に,『処罰と近代社会―社会理論の研究』(翻訳,現代人文社,2016年),「厳罰傾向と帰属スタイルの関連―日韓の比較から」(共著,『心理学研究』91(3): 183-192,2020年),「特定少年実名報道への支持と,責任付与・改善更生・重大性に関する各認知との関連」(共著,『心理学研究』95(2): 119-128,2024年)など。
相良
あの本に日本の話も出てきていますものね。
向井
そうですね。日本がむしろメインぐらいの扱いでオーストラリアと比較されているのですが,それすら訳されていません。そういう古典が訳されていないのが犯罪学とか刑事司法に関する研究の現状で,あまり研究が進んでない原因になっている気はしますね。
相良
ニワトリが先か卵が先かの話かもしれないけど,気にはなりますよね。
向井
そこまで興味がない人とか,初学者の人や学部生とかは,日本語の方をまず読んでみて,それで関心をもって大学院に行ったりして研究をすると思うので,翻訳されてないために入り口に入りづらくなっていて敷居が高くなっている現状はかなり憂慮すべき感じがしますね。
相良
たしかに。
――研究者であれば,おそらく原著を大学院で読まれる方がほとんどだと思いますけど,学部生からすると訳されているかどうかは非常に大きいですよね。
向井
大きいと思います。まあ研究者もなかなか原著では読まないですからね。日本語に翻訳したら読む人は増えると思いますけれども。翻訳されているかどうかによって知識量はかなり変わりますよね。
相良
そのとおりですよね。
向井
さらに言うと法学者はけっこう英語を読まない人が多いですからね。ドイツ語とかフランス語をバックボーンにしてる人がかなりいるので。英語は意外と得意ではない人が多いかもしれません。
相良
そうですよね。教科書で出てくる本でも訳されてないものがありますよね。
向井
あと逆に訳されているのが教科書で使われやすい側面もありますよね。だからブレイスウェイトとか,意外と犯罪学の教科書に載っていない気がします。教科書を書いている人もじつは読んでないのではと思うこともあります。
相良
たしかにブレイスウェイトは修復的司法でも著名だから,訳されていてもいいかなと思います。
向井
そうですね。
相良
今回の本も32年前の本ですから,これぐらいタイムラグがあって翻訳される本はあまりないような気もします。僕がこの本を知ったのが大学院生(上智大学大学院総合人間科学研究科社会学専攻博士前期課程)のときだったんですよね。修士課程に入った頃の指導教員が上智大学の田淵六郎先生で,先生は家族社会学やライフコース論の専門でしたが,僕の研究テーマを聞いて,「この本はどう?」と紹介してくれました。そのときに思ったのは翻訳書が欲しいなだったので,そのときの自分を読者層に考えて訳したというのはあります。正直,修士のときはあまり勉強できていないし,英語も読み慣れていないし。なにより社会福祉から社会学に専攻が変わったので,一から社会学の勉強をしなおしたので,修士のときには学び切れなかった。今回もそのときに買った本を使いながら翻訳しました。
1つ笑い話があって,そのときに買った本にページの抜け落ちがあって,その当時は全然気づいておらず,今回翻訳したときに気づくというね(笑)。いかに読んでいないかがばれるんですけど。
向井
珍しいですね。
相良
序盤の方で4ページぐらいから抜けていたのに,そのまま読んでいたようです。メモ書きもしてあったので,変だなと思ったんでしょうけど。
おおげさかもしれませんが,翻訳書があったら人生が変わってたかもしれないですね。
向井
こんな面白い研究があるのかと。たしかに大学院ぐらいのレベルかもしれないですね。現代においては,統計的にもそれほど難しいわけではないので,社会学に関心をもっている大学院生の方にはたしかにいいかもしれないですね。ゼミとか勉強会とかで読んでいただくのに合っている気はします。
――そうですね。
向井
読む際に気をつけるところもあるというか,いまでは古くなっているところもあると思いますので,そういうところをお互い勉強しながらやるような読み方がいいのではないかなという気が個人的にはします。
相良
古さという意味では,たとえば統計手法が1993年としては妥当なものであったと思いますが,いまからすると時代遅れ的なところがある。あと訳者あとがきを書くうえで,いろいろとレビュー論文を読んだのですが,ラウブとかサンプソンのその後の研究の話にもつながってくるんですけど,ラウブはとくに公共政策にこの知見を生かそうとしていたという話があって,家族支援のあり方にも提言をされたようです(2)。彼らの知見や根拠からすると,家族への着目は妥当なところなのかなと思いますが,そこに過度な期待をもたらしうる点はちょっと気になったところですね。他には,今回のデータが1930年代生まれの男性中心だったので,そういう意味では偏りは当然あって,偏りがあるからだめなわけではないですけど,男性性(マスキュラリティ)の意識の下で論じられてはいないので,そういう検討があってもいいだろうということは訳者あとがきに書きました。
――男性性の意識っていうニュアンスを少しお話しいただけると。
向井
僕もちょっと思ったのは,データをとるときに親の監視や見守りの変数がありましたが,女性,つまり母親がする見守りや子育てしか変数としてとっていません。男性と女性の性役割分業を感じましたね。そういうところですかね。
相良
サンプソンとラウブというより,元のデータをとったグリッグ夫妻の価値観かもしれません。サンプソンたちもこの本の中でその話に触れていて,その当時の性別役割分業の価値観を踏まえて,そういう変数を決めたという話が出ていたかなと思います。そういう古臭さというか,限界の下でのデータというのがありますよね。男性性についていうと,たとえば,結婚というイベントに関して,便宜的に異性間の結婚を前提に話しますが,男性が経験していることと女性が経験していることの意味に違いがあって,結婚が犯罪や逸脱行為へのストッパーになるという知見もその後の研究で,女性の離脱には結婚は意外と効かないという研究がある。男性のそういう社会的なポジショナリティの下での経験と,女性のポジショナリティの下での経験ではやはり意味や影響が違って,離脱に効くかどうかにも関わってくる。
向井
要するに男性にしかあてはまらない知見である可能性があるということですね。男性しかサンプルをとってないわけですので,男性に限らず,他の文化や他のサンプルにあてはまる知見かはわからない,そういう限界があるという話ですかね。
相良
そのとおりですね。吉間さんや大江さんは何かありますか。
吉間
時代背景の問題とこの調査の問題でもあるとは思いますが,この研究は社会経済的地位が高くない人たちを追跡しているので,そこは留意が必要だという気がしています。ホワイトカラー犯罪に関する研究や批判的犯罪学などが指摘してきたことですが,犯罪をしている人たちは社会的経済的地位にかかわらず分布しているのに,犯罪者化されて刑事司法の対象になる人は社会経済的地位の低い人々に偏っている,つまり,刑事司法は特定の地位にある人々に不利に働く制度だということです。この本はその批判を正面から受けることになると思います。そもそもこの研究で従属変数として扱われている犯罪という概念は,これも批判的犯罪学で指摘されているところですが,社会経済的地位の高い人が社会に重大な害悪を与える行為は犯罪と定義されず,社会に比較的小さな害悪しか発生させない街頭犯罪ばかりが犯罪と定義されているという問題も抱えています。これらのような点に留意しないと,刑事司法制度がもっている不平等性を強化しかねないと思うので,注意して読む必要があると思っています。
吉間慎一郎(きちま・しんいちろう):検事。主要著作に,『更生支援における「協働モデル」の実現に向けた試論―再犯防止をやめれば再犯は減る』(LABO,2017年),「社会変革のジレンマ―伴走者と当事者の相互変容からコミュニティの相互変容へ」(『犯罪社会学研究』44: 46-62,2019年),「包摂と排除をひっくり返す―解放区からの変革可能性」(『犯罪社会学研究』49: 25-39,2024年)など。
相良
そうですよね。第1章の注2で犯罪概念に関して書いてありますが,基本的には「法律に体現された社会的行動の規則の違反と定義するという慣習に従う」ということなので,吉間さんが話された既存の犯罪概念に従うっていうのは前提で進められてはいますよね。ゴットフレッドソンとハーシの本を引用しながら,「一般的な含意がある」と書かれているので,たぶんそれ以上のことは書かないことにしているのでしょうね。たしかにおっしゃるとおり批判の対象になるかなと。
吉間
それから,翻訳する過程でもたしか出てきた話ですけど,犯罪と並んで従属変数となっている酩酊が意味するものについては,留意して時代背景を踏まえる必要があるかもしれません。クラックコカインなどの比較的安価で,使いやすい薬物が流行する前の時代では,その後の時代と比べて逸脱行為が飲酒として現れやすい可能性がありますよね。
向井
あと怠学もそうですよね。学校に行かないことって別に,法律の違反ではない気はします。怠学も非行の変数に入ってましたよね。
相良
そうですね。彼らは犯罪だけじゃなくて問題行為みたいなものも含めて論じるっていう宣言したうえで研究を進めていますね。だから犯罪だけにとらわれず,いわゆる虞犯みたいなものも含めて分析するという形にはなっていたはずですが,そのあたりの妥当性ですよね,そもそもの設定として。
――この研究に限らず,どうしてもその研究がされた時代背景の影響は必ず受けますよね。現在行われている研究であっても現在の時代背景を受けているとは思うのですが,そのあたりをどこまで一般化できるのだろうというのは,犯罪研究の場合は常に大きな問題だという感じはありますよね。
相良
おっしゃるとおりですね。
向井
おそらく吉間さんの問題意識としては,そもそも法律の定義に従って犯罪を定義していいのかということですよね。批判的犯罪学の人からしたら,そもそも犯罪の定義がいま処罰されていることが犯罪とされるのはおかしいという議論があって,法律上の定義に従って犯罪定義する考え方はアドミニストレイティブ・クリミノロジーとか呼ばれます。つまり,行政管理的な上から目線で「犯罪はこういうものだ」と定義してしまうので,それを批判する人もいますね。これは犯罪学者のガーランドやヤングという人がしている批判なのですが,そうした人の批判を本書はもろに食らうことになるでしょうね。もちろん,立場の置き方かなという気はしなくもないので本書がただちに悪いとは個人的には思わないですけどね。ただ,留意した方がいいのはたしかですよね。
相良
新たな示唆というのはなかなかこの本からは難しいかもしれません。むしろ,ここで言われている知見がどうやって現代の司法に取り入れられているのか,それぞれ読者のみなさんに確かめてもらうのが大事だと思います。結婚とか仕事をすればOKというわけではなくて,むしろこの本の中で述べられているのは,仕事とか結婚を通じて何を得ているのかってところですよね。そのプロセスや影響の方がとても重要なので,そこを吟味してほしいです。「サンプソンとラウブは結婚と就職が離脱に効くとする」というような引用だけにとどまらないようになったらいいなと思います。そのために翻訳しましたので。正確に読むといろいろなことが書かれていると思います。就職の質や結婚のあり方,その時代背景,それも加味したうえで,答えを出すっていうことですね。研究者であれば,なんとなくみんなが引用でこの本の内容を知っていると思いますが,その内実を知ってもらって,じつはそれほどシンプルでもないということを把握してもらえるのが,いいのではないかなと思います。それはおのずと,犯罪対策へも少しは影響するかなというところですね。犯罪対策が多少なりとも進んでいるけれども,彼らが言っているとおりにやっているのか,やっていたとして本当にこう変わるのかとか,新規性というよりも,振り返りになる契機になる本かなという気はしています。そこが古臭さであって,新しさでもあるのかなと。新しく振り返る機会をくれる本になるとよいですね。
――研究者の方でも読み直してみて,こういうことをやっていたんだとか,言っていたんだっていうことに気づく方も,もしかしたらおられるかもしれないので,そういう意味でも日本語で読める,気軽に読めるというのはすごい大事なことなんだろうなと思います。
相良
おっしゃるとおりです。界隈で有名だからこそ,知見がシンプルに取り扱われているところがあったと思うので。
吉間
思い返すと,相良さんにこれを訳さなければいけないですよねって話をしたのは,そういう理由だったような気がします。
相良
そうそう,けっこう前のことなので忘れかけていたけど。全面的に賛成するわけではないけど,重要な知見になってるからこそ細かく読んでほしいみたいな。
吉間
そうですよね。
相良
賛同するのは賛同するのでいいし,批判するのは批判するのでいいし,それで研究が広がっていくところはありますよね。研究者であれば,英語で読めるようになりなさい,という話かもしれないですけど。重要文献の翻訳が足りていないから,研究が広がりにくいのだろうなというのは思っていました。そんなことを吉間さんと話していて,離脱の研究を吉間さんも僕もやっていて,その流れの中でこの本の翻訳があったらまた変わるよねという感じで話をしましたね。むしろ一番肝心なとこだよね。新しい知見として読まれたくはないなというのは僕もやはりあったので。この本に対する批判があって,より犯罪学や学問が広がっていくのもいいかなと思います。
向井
かりにこの研究の定義をさらに広げて,あるいは狭めるかして変えたら,けっこう変わりますかね。いまやるとすると従属変数をどうするかとかも,関心はありますね。いまの日本に合わせて,この研究を批判して次につなげるとしたらどういう変数を入れたり,逆に除外したりするんですかね。こんな感じで考えるのってすごい勉強になると思いますので,読んでいただいていろいろと勉強会とかで使っていただくといいかもしれないですよね。
相良
犯罪などの概念を解体した後に再構築は求められるはずなので,そうなったらどうなるんだろうっていうのはたしかにありますよね。定義の中にある変数にも,外してもいいのではないかと思うようなものもありますよね。怠学を入れる必要があるのかとか。
向井
嘘とか反抗的とかも外してもいいかもしれないですね。
相良
そのあたりって,実害としてはたいしたことないのではと思うところもありますよね。
(所属は出版時のもの)
文献・注
(1) Braithwaite, John, 1989, Crime, shame and reintegration, Cambridge University Press.
(2) 上野貴広,2007,「犯罪学におけるライフコース・パースペクティブの台頭と展開――サンプソン=ラウブの所説を中心に」『北九州市立大学大学院紀要』20: 155-202.
何が少年たちの人生を分けたのか? ライフコースを通じて,犯罪や逸脱行動を繰り返す人と犯罪や逸脱行動から離脱する人とを分ける要因は何か。多面的な指標が含まれる,グリュック夫妻による1000人の長期縦断調査データを再構築・再分析し,年齢に応じたインフォーマルな社会統制理論を提唱した記念碑的名著。