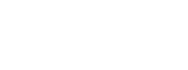性格を2回尋ねると回答は変わる?――再検査効果の検討
『パーソナリティ研究』内容紹介
Posted by Chitose Press | On 2025年04月09日 | In サイナビ!, パーソナリティ研究質問に繰り返し回答すると,2回目の回答が1回目の回答よりも社会的に望ましい方向に変化する「再検査効果」がいくつかの研究で報告されています。性格特性に関して再検査効果が生じるかどうかを調べるために、オンライン調査が実施されました。(編集部)
上田皐介(うえだ さすけ):名古屋大学大学院教育発達科学研究科・日本学術振興会特別研究員PD。→webサイト
再検査効果
人々の性格は比較的安定したものとされています。しかし,性格を測定する質問に複数回答えると,2回目の回答が1回目よりも社会的に望ましい方向に変化する「再検査効果」という現象がいくつかの研究で報告されています。
これまでの研究の問題
再検査効果や,性格について繰り返し尋ねることの影響を調べた研究は少ないものの,いくつかあります。それらの多くでは,参加者は2時点ともに,性格についての質問に答えます(このような調査・実験の方法を参加者内計画と呼びます)。そして時点1と時点2の回答を比較します。しかし,これには問題があります。それは,もし時点1と時点2の間で変化があっても,「2回同じ質問に答えたことの影響(=再検査効果)」によるものか,「季節や行事など時点間での様々な要因の違い」によるものかはわかりません。たとえば,外向性の自己評価が時点1より時点2で高くなっていたとしても,それは季節が変わり気温が上がったことで外出の機会が増えて自己評価が変わったのかもしれません。
今回の研究で問題をどのように解決したか
この研究では,「時点間での様々な要因の違い」が生じないようにするために,参加者を無作為に2つのグループ,「1回条件」と「2回条件」に分けました(図を参照)。どちらの条件も2時点とも調査に参加してもらいました。1回条件の参加者には,時点1では食べ物に関する質問に,時点2では性格を尋ねる質問に答えてもらいました。性格を尋ねるのが1回なので「1回条件」と呼んでいます。2回条件の参加者には,時点1と時点2の両方で,性格についての同じ質問に答えてもらいました。性格を尋ねるのが2回なので「2回条件」と呼んでいます。そして,時点2での性格の回答をグループ間で比較します(参加者間計画と呼びます)。この場合,「2回条件」で「1回条件」よりも性格の回答が望ましければ,再検査効果がみられたといえます。
図
なお,我々が研究を行う少し前に海外の研究チームが,似たような着想で参加者間計画の研究を発表しました(Anvari et al., 2023, 2024)。その研究では「2回条件」は我々の研究とほぼ同じである一方,「1回条件」に相当するグループでは,時点1は何にも回答しない,つまり調査に参加しません(なので彼らの論文では,前者を「開始が早い条件」,後者を「開始が遅い条件」と呼んでいます)。この方法では,季節など「時点間での様々な要因の違い」は生じないものの,2つのグループの差の意味が定まりません。つまり,2つのグループの差分は,「性格についての同じ質問に2回回答したかどうか」ともいえますが,「調査に2回参加したかどうか」や「時点1で何らかの質問に回答したかどうか」でもあるため,2つのグループに差がみられても再検査効果以外の理由で解釈できる可能性が残ります。そこで,我々の研究では「1回条件」を設定しました。
調査の概要
今回は,性格特性の中でも広く研究されているビッグ・ファイブ(神経症傾向,外向性,開放性,調和性,勤勉性)において,この再検査効果が生じるかどうかを検討しました。
調査はオンラインで実施し,日本国内の20~69歳の成人1,823名(1回条件:930名,2回条件:893名)にご参加いただきました。時点1と時点2の間隔は1週間としました。
結果
分析の結果,どの性格特性においても再検査効果はみられませんでした。すなわち,時点2の回答について,グループ間に統計的に意味のある差はみられませんでした。また,2回条件の時点1と時点2の回答を比較しても(=参加者内計画による比較をしても),回答に差はみられず,これらの結果からも再検査効果は確認されませんでした。なお,先ほど紹介した研究でも(Anvari et al., 2023, 2024),同様に再検査効果はみられていません。
限界と今後の課題
我々の研究はオンラインで実施した一方で,これまでの研究は対面で行われており,回答環境の違いが影響している可能性があります。また,オンライン調査の参加者は,日常的に性格に関する心理学調査に参加しており,「回答慣れ」している可能性も考えられます。今後はこれらの要因と再検査効果の関係を調べる必要があります。さらに,時点間の間隔を変えた場合の結果も調べる必要があります。
この研究の重要性
再検査効果がないかもしれないという結果は,性格の変化を扱う研究にとって重要な知見といえます。従来,性格は変わりにくい(=安定している)とされてきたものの,近年のパーソナリティ心理学の研究では,性格が変化することが明らかになりつつあります。性格を変えたいと思い,「トレーニング」に取り組むことで変化することが繰り返し報告されています。こうした性格の変化を扱う研究では,トレーニング前後で性格について質問し,変化を推定します。その際,本当に性格が変わったのか,それとも再検査効果の影響であるかを区別する必要があります。これを検討する方法として,トレーニングをしたグループの比較対象として,何もしないグループ(=統制条件)を設けることがありえるものの,倫理的な観点から毎回設けられるわけではありません。統制条件を設けることが難しい場合には,今回の研究のデータや結果を,(少なくともオンラインでのトレーニングにおいては)簡便な比較対象として活用できる可能性があります。
本研究は性格の変化を扱うすべての領域に貢献すると考えています。
引用文献
Anvari, F., Arslan, R. C., Efendić, E., Elson, M., & Schneider, I. K. (2024). No initial elevation on personality self-reports in an online convenience sample. Collabra: Psychology, 10 (1), Article 117096.
Anvari, F., Efendić, E., Olsen, J., Arslan, R. C., Elson, M., & Schneider, I. K. (2023). Bias in self-reports: An initial elevation phenomenon. Social Psychological and Personality Science, 14 (6), 727-737.
文献
上田皐介・山形伸二 (2025).「事前登録研究:Big Fiveの再検査効果――参加者間・参加者内計画を用いた検討」『パーソナリティ研究』33(3), 179-181.