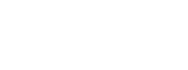超高齢社会のモノづくり・デザイン
つくば型リビング・ラボの挑戦
発行日: 2025年11月30日
体裁: A5判上製296頁
ISBN: 978-4-908736-44-5
定価: 3200円+税
ネット書店で予約・購入する
内容紹介
高齢者と探るモノの使いやすさ
どのように高齢者と協働して「モノの使いやすさ」を探究するのか。参加者データベースの構築と活用,ユーザビリティテストや家庭訪問調査の実施,高齢者と開発者との議論、コミュニティ活動の運営など,「みんラボ」の実践例と方法論を示す研究実践カタログ。
目次
序章 みんラボという試み――対話形式による概要の紹介
第Ⅰ部 超高齢社会と使いやすさ
第1章 ユニバーサルデザインと認知的加齢
第2章 日常生活でのユーザエクスペリエンスをいかに捉えるか――リビング・ラボの可能性
第Ⅱ部 つくば型リビング・ラボの方法論カタログ
第1章 使いやすさを「議論する」――みんラボカフェ
第2章 使いやすさを「尋ねる」――インタビューと質問紙
第3章 使いやすさを「観察する」――家庭訪問
第4章 長期間の利用を「観る」――長期継続型ユーザビリティテスト
第5章 使いやすさの要因を「調べる」――実験計画に基づくユーザビリティテスト
第6章 個人特性との関連を「探る」――みんラボデータベース
第7章 モノづくりを「実践する」――ユーザ参加型デザイン
はじめに
「十年ひと昔」という言葉があります。最近,「ひと昔」の「ひと」は「ごく小さい」という意味であり,でも同時に「きちんとその実体がある」の意味でもあるのだな,と思うようになりました。筑波大学で始めた「みんラボ」,正式名称「みんなの使いやすさラボ」を設立してからいつの間にか10年を超え,15年の「それなりの重みのある歴史」ができていました。この本は,その経験を少しでも「後の世代や他の地域の方々にも伝えたい」という思いで編ませていただきました。
その思いの底にあるのは,「頑張って,自分たちなりに社会につながる研究を実践してみました」,そうしたら「こんなことができました,こんなこともわかりました」というメッセージです。「類は友を呼ぶ」とでも言いましょうか,みんラボの登録会員となってくださる高齢者のみなさん,手を差し伸べてくださっている研究者や学生のみなさん,仲間になってくださった企業や組織,とりわけコンソーシアム会員になってくださったみなさん,さらには「応援団」とでもいうべき「陰に陽に,我々の試みを励ましてくださる」みなさん,いずれにも共通することが,「社会に役に立つこと,社会につながっていくこと」をよしとする価値観,そしてそれを実現するための1つのアプローチとしての「研究という活動」を大切に思ってくださっていることと感じています。
「社会に役立つ研究」というフレーズをお題目として扱うのではありません。それを実行,実現するためには,1つのやり方,マニュアルに沿っていけばよいのではなく,自分たちが何を目指しているのか,目指すべきなのかを考えながら,1つずつ決めていく必要がありました。「社会につながる,社会に役立つとはどういうことだろう?」「社会って何を指すのだろう?」「研究するとはどんな活動なのだろう?」といったことをつねに考えながら,自分たちの進む道を決めていく,それはとても「手間がかかる」,あまり効率的ではないアプローチです。しかし,いわゆる「正解がない」あるいは「正解はいたるところにある」課題を解決していこうとするときには,つねに「自分たち自身で,試みを通じて,つねに新しい方法を築いていく」必要性があるのだと思います。その意味で,こうした活動はある意味で,民主主義の実現,継続ととても似ているなとも思っています。そういえば,「みんなの」使いやすさラボという名称,あるいはリビング・ラボという方法論からも,「民主的な研究とはなんだろう?」という問いが,その根本にありますね。
10年,15年経ってもこのくらいのことしかできないのか,と思われるかもしれません。正直なところ,日本の中の一地方の小さな活動にすぎません。しかしこの蓄積は,何か自分たちが大切だと思うことを実現していくことは,こういう形でできていくのだ,ということを実感した活動の履歴でもありました。
とはいえ,みんラボでの活動のすべてをここに記すことはできませんでした。ここでは,みんラボで取り組んできた「研究」という活動が,どのようなものであるのか,とくにどのような方法論が利用できるのか,そこでどんな可能性があるのかを示すための「研究実践カタログ」をお届けすることになりました。みんラボというコミュニティとしての活動,人材育成の側面,こうしたグループ,組織体の運営(の難しさ!)などなど,他の要素については,また別の機会にご紹介させてください。
ということで,「みんラボ」で経験した「研究」という活動について,ご紹介します。ぜひお楽しみいただき,いろいろとご意見を聞かせてください。