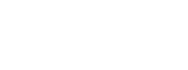批判的犯罪学
刑事司法と犯罪研究を問い直す
発行日: 2025年9月20日
体裁: 四六判並製280頁
ISBN: 978-4-908736-42-1
定価: 2600円+税
ネット書店で予約・購入する
内容紹介
不均衡な犯罪概念を批判する
刑事司法制度と主流派の犯罪学は,犯罪概念の有する不均衡や権力性を容認・黙認し,力なき人々を虐げ続けている。この現状に対して,私たちは異議を唱えたい。ここに日本版批判的犯罪学の「綱領」を掲げ,刑事司法と犯罪研究を問い直す。そして,公共的な討議の場を求める。
目次
第Ⅰ部 批判的犯罪学の視角
第1章 日本版の批判的犯罪学――綱領とその解説 ■山口毅
第2章 批判的犯罪学の傾向と実践――研究領域の広がりと奥行き ■山本奈生
第3章 被害者研究と研究者の実存をつなぐ――価値中立性,批判的犯罪学,オートエスノグラフィ ■岡村逸郎
第4章 批判的犯罪学とソーシャルハーム概念――ゼミオロジー/ソーシャルハーム・アプローチの問題提起に注目して ■山口毅
第Ⅱ部 批判的犯罪学の展開
第5章 社会変革としての刑罰廃止論 ■吉間慎一郎
第6章 刑事法研究者は批判的犯罪学の主張をどう受けとめるべきか ■松原英世
第7章 刑事司法の根源的な批判へ――食糧管理法違反のケースから ■盛田賢介
第8章 逃げながら闘う――ラベリング,社会的犯罪,フィルム・ノワール ■渋谷望
はしがき
批判的犯罪学とは何か
批判的犯罪学は、既存の刑事司法制度や主流派の犯罪学を批判する集合的実践の総称である。刑事司法制度や主流派の犯罪学・犯罪社会学は、犯罪概念に依拠しているが、そもそも犯罪概念は不均衡が伴ってはいないだろうか。
犯罪という概念は、刑法(本稿での刑法は、犯罪と刑罰を規定するすべての法を指す)によってあらかじめ定められている。そして、いまある刑法はおよそどの国でも、権力者や多数派にとって有利なように決められ、力なき人々にとって不利に形成されている。たとえば、窃盗罪は主たる「財産犯」なのだが、その逮捕者はだいたいのところ、裕福ではない人々に偏っている。一方で、死に至るほどの厳しい労働環境を用意し、実際に自殺者を出させたような経営者層や、多くの環境破壊をもたらした企業や行政の責任は、一部の事例を除けばだいたいは刑法の適用対象外である。
私たちは、いまある刑法によって定められた犯罪概念に依拠する研究には、二つの点で問題があると考えている。第一に、もともと経済的・政治的・文化的に弱い立場にある人々を対象としがちな、刑事司法制度の不均衡を結果として黙認するという問題がある。アメリカでのよく知られた事例として、昔から警察による暴力の対象とされがちだった、黒人の人権問題はわかりやすい出来事だろう。アメリカの刑務所は膨大な収監者を抱え、しかもその多くは、人口比率から見て黒人やヒスパニックに顕著な偏りがあり続けてきた。「ブラック・ライヴズ・マター」運動で言われてきたように、多くのマイノリティが警察からの暴力によって死に至らしめられてきたという事実がある。日本の受刑者にも、経済的格差などの偏りはおおいに関係している。
第二に、既存の犯罪概念では、公害、気候危機、労働環境の悪化、経済や社会の不平等を問題化しきれず、権力者による「犯罪的な営為」を見逃してしまいがちである。戦争、水俣病や大気汚染などの公害、自動車産業の拡大が生んだ膨大な自動車事故、製薬会社がもたらした薬害、原発事故、政界の不正などのほんの一部しか、犯罪概念では捉えられていない。政治家、行政、軍による悪事、入管施設での不当な扱い、技能実習生の待遇の問題から、企業がもたらす過労死に至るほどの労働環境まで、多くの事柄が犯罪概念の外部に置かれてきた。
だから批判的犯罪学は、一つ目に刑事司法制度が生み出してきた苦しみや痛み(その背景にある人々に与えられた害=ハーム)を問題とする。つまり、不均衡な制度からの摘発や暴力を受けた人々の叫びを、取り上げようと試みるのである。刑事司法制度と似たような事柄も含めて、ここには「奴隷制に反対して暴行された、奴隷の声」から、入管施設で虐待された「不法移民の声」までが含まれうる。
二つ目に、日本を含む「経済大国」は大きな格差を擁し、また気候危機や公害、戦争、金融資本主義から生ずる諸問題にうまく対処できていないことを問題とする。ところが、どの社会の刑法も、これらの問題に対してストリートの窃盗者と同じような「責任者の処遇」を行っているようには思えない。日本では東京電力の起こした原発事故は、刑法上の「犯罪」として認定されておらず、ベトナムやガザの戦地で生じた惨禍について、大部分の政治家や将校は責任をとっていない。
念のために言えば批判的犯罪学は、不正を行った企業経営者や政治家を刑務所に収監すれば、多くの問題が解決すると言っているのではない。刑罰や犯罪というカテゴリーの土台が不均衡だと言っているのである。世の中にはハームが至る所にあるのに、刑法と犯罪概念は、社会構造の問題を等閑視しつつ、力なき人々の行為を問題化しがちである。
既存の犯罪概念に依拠して「犯罪」を対象とする主流派の犯罪学や犯罪社会学は、「元受刑者を優しく更生させるような地域社会が望ましい」とか、「刑務所収監者に貧しい人が多いことは問題だが、一方で罪は罪である」などと論ずることが多い。これらは厳罰化を批判するリベラルな振る舞いだと言えるが、同時に既存の犯罪概念にしがみつこうとしている点において、犯罪概念の土台にある不均衡を黙認する結果をもたらしている。
批判的犯罪学は、このように既存の犯罪概念が有する不均衡や権力性を批判する人々によって、一九七〇年代の欧米から始発した集合的実践の総称である。批判的犯罪学という営為は、欧米のみならずグローバルサウスを含めて一定の地歩を得てきたのだが、日本の犯罪学や犯罪社会学ではほとんど無視されてきた。この現状に対して、私たちは異議を唱えたい。本書は、「批判的犯罪学」という言葉をタイトルに含む、日本ではじめての著書である。本書は、欧米での批判的犯罪学の研究の蓄積を踏まえつつ、批判的犯罪学を、私たちの視点から一つの学派(いわば日本版批判的犯罪学)として打ち出す。本書は、批判的犯罪学の視角を提示してその可能性を検討する、集合的な挑戦なのである。
私たちは、あらかじめ決められた刑法概念に依拠して実体的な行為・属性として「犯罪」と「犯罪者」を捉える見方を、批判する。すなわち「犯罪」と「犯罪者」を、刑事司法の関係者と研究者の特定の価値に根差し、恣意的なかたちで作り上げられるカテゴリーとして捉える。そして刑事司法は、万人を平等に扱うものではけっしてなく、権力者にとって有利で、社会的に弱い立場に置かれる人々にとって不利になる偏った働きをする、政治的な装置として位置づける。
批判的犯罪学は、既存の犯罪概念を根本から問い直し、それをたとえば「ソーシャルハーム」といった、まったく別種のカテゴリーの下で捉え返す点に特徴がある。そしてある個人や集団が他者に与えるハームを、刑事司法と研究者がもたらすものも含め、別様のアプローチから把握しようとする点に特色がある(Hillyard and Tombs 2004など)。
批判的犯罪学研究会と、本書の構成
私たちは、本書の第1章で述べるように、批判的犯罪学を、「犯罪」を扱う制度と学知のあり方を問い直し、研究者がみずからの規範的コミットメントを明示したうえで話し合う公共的な討議の場を求める学派として捉える。さらに、「犯罪」の原因や責任、解決を個人の水準ないし個人への働きかけの水準で考える立場を批判し、社会の変革を志向する学派として位置づける。そしてオルタナティブな研究の視角を提示し、刑事司法の廃止論(アボリショニズム)というラディカルな立場も念頭におきつつ、「犯罪」を根本的に考え直す。
本書の構成は、以下のとおりだ。第Ⅰ部「批判的犯罪学の視角」では、意見交換によって共通の指針として作られた綱領を紹介し、批判的犯罪学の視角に関する総論的な内容が各章の執筆者の視点から記述される。第Ⅱ部「批判的犯罪学の展開」では、批判的犯罪学の視角に依拠する各論的な内容が各章の執筆者の問題関心と研究テーマの下で展開される。
本書の各部と各章は、緩やかな横のつながりをもちつつ、それぞれが独立して読める内容になっている。批判的犯罪学の理論的ないし方法論的な内容に関心がある読者は、第Ⅰ部から読み進めていただくのがよいだろう。まずは具体的なテーマや対象に関心がある読者は、第Ⅱ部の中の関心がある章から読み進めていただいてもかまわない。
第1章「日本版の批判的犯罪学―綱領とその解説」では、「刑事司法と主流派犯罪学への批判的視角」、「研究者の規範的コミットメントの明示と検討」、「個人化の拒絶と社会の変化に対する要請」という綱領の三本柱が扱われ、解説が付される。そこでは綱領が、主流派犯罪学と厳しく対立する性質をもつことが示される。その上で、批判的犯罪学の運動への参加あるいはその主張への反論が呼びかけられる。
第2章「批判的犯罪学の傾向と実践―研究領域の広がりと奥行き」では、批判的犯罪学と目されうる潮流への解説がなされ、日本の文脈と欧米の研究動向が整理されている。そして、批判的犯罪学はどうしても実存の問題と切り離せないことが強調されている。
第3章「被害者研究と研究者の実存をつなぐ―価値中立性、批判的犯罪学、オートエスノグラフィ」では、研究と実存の問題を、犯罪の被害者かつ研究者として生きる執筆者の実存を記すことを通して考える。そして、研究と実存の問題を批判的犯罪学の視点から考える際にヒントをくれる視点として、オートエスノグラフィを検討する。
第4章「批判的犯罪学とソーシャルハーム概念―ゼミオロジー/ソーシャルハーム・アプローチの問題提起に注目して」では、批判的犯罪学内外での議論が整理される。研究対象としてのソーシャルハームを扱う際には、研究者の用いる規範の検討が必要だと論じられる。そして規範としての刑法や法・権利に関する批判的犯罪学のスタンスが考察される。それと同時に、主流派犯罪学が往々にして規範的な自省を欠落させ、不備を抱えてきたと主張される。
第5章「社会変革としての刑罰廃止論」では、刑事司法が植民地主義と同型の論理で特定の人々を抑圧する不平等な制度であり、平等な社会を目指す社会変革の一環として刑罰廃止が目指されなければならないと主張される。社会変革としての刑罰廃止論とは、人々の苦痛の除去と補償がなされるオルタナティブを求めて、刑事司法や伝統的法学が矮小化し市民から奪ってきた紛争解決を取り戻し、正常と異常とを分け隔てている規範を問い直す実践であることが示される。
第6章「刑事法研究者は批判的犯罪学の主張をどう受けとめるべきか」では、刑事法研究者は批判的犯罪学の主張をどう受けとめるべきか」では、批判的犯罪学の主要な批判対象の一つである刑事制度を研究する者として、彼らの主張への応答を試みる。刑事法がコミットする価値を前提とすればこうなるはずだという仕方であるべき刑事制度に言及しながら、彼らとの共闘の可能性を示したい。
第7章「刑事司法の根源的な批判へ―食糧管理法違反のケースから」では、近年進む司法と福祉の連携を批判的に問い直す。司法と福祉の連携が可能になる制度的な条件を、戦後直後の食糧管理法違反のケースから考察する。その後、批判的犯罪学の知見を借り受けながら、司法と福祉の「幸福な結婚」を切断し、よりラディカルな方向へ福祉が進むべきことを提起する。
第8章「逃げながら闘う―ラベリング、社会的犯罪、フィルム・ノワール」では、犯罪映画のジャンル、フィルム・ノワールの典型的な主人公「逃亡者」が出現した背景として労働運動および民衆運動の歴史を検討し、批判的犯罪学―ラベリング論と社会的犯罪論―の視点が、逃亡しながら闘う人々の実践に根ざしていることを明らかにする。